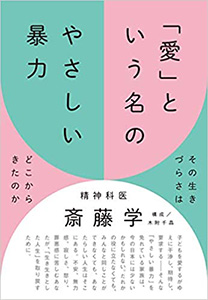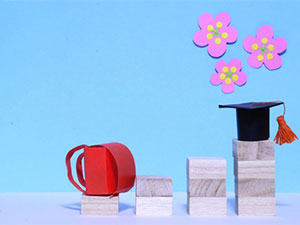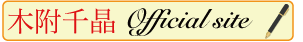発達障害という言葉は、ここ数年、ニュース等で取り上げられたり、著名人がカミングアウトしたりと、ずいぶん身近なものになってきたように感じます。
ですが、まだまだ誤解されがちな部分もありますし、「そうかもしれないけどどうしたらいいのだろう」というところで止まってしまっている、という方も多いように感じます。
そもそも発達障害とは
コミュニケーションが苦手である、こだわりが強い・感覚の過敏さがある、集中が続かず要領よく物事を進められない、といったお悩みが代表的なものとして挙げられます。
コミュニケーションの苦手さ・興味の幅が限定される等は自閉症スペクトラム(ASD)、注意散漫さはADHD(注意欠陥多動性障害)の方に多く見られる傾向です。
アスペルガー症候群という言葉も一般的に知られていますが、これは自閉症スペクトラムというカテゴリーに含まれていますので、ほぼ同意語と考えてよいかと思います。
発達障害の原因は?
かつて「自閉症は親の育て方が悪かったのではないか」という誤解がありましたが、最近は正しい理解がだいぶ広まってきたように感じます。
発達障害は、生まれつき持った特性であり、脳の一部の機能に障害があると考えられています。
ですので、発達障害は‘人生の途中で突然発症する’というものではないですし、逆に言いますと根本的な治癒をめざすものでもありません。
その特性を知り、その特性とともにどう日々を過ごすか、どうすればより良く過ごせるか、を考えていくことが重要です。
発達障害の診断
診断は、医師による問診・心理検査・その他の情報(お子さんの場合は保護者の方からの聞き取り等)を総合して行われます。
CAFICは医療機関ではありませんので診断はできませんが、前述の「心理検査」の部分を行うことができます。この検査がどういうものかについては、また別の機会にもう少し詳しくご説明したいと思います。
CAFICでおこなえる支援
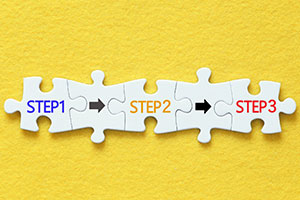
お子様の場合は、発達特性があることによって集団生活での適応が難しくなりがちですし、養育される保護者の方の心身のご負担も重くなることが多いと言えます。
CAFICでは、検査だけでなく、保護者の方への心理的サポートや環境調整に関する助言(学校やその他機関とどう関わっていくべきか)等もおこなっています。
おとなの方の場合は、ご自身の特性を把握し、現在お困りの事柄についてどう対応していくか、カウンセリングを通してそのサポートをおこなう形になります。
大事なのは、検査の‘その後’――つまり「その方が自分らしく、よりストレスの少ない日々を過ごせるようになること」ではないでしょうか。