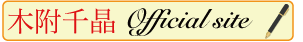CLUBみなしご 情報共有
ファシリテーター紹介

クラブみなしごのファシリテーター・青木智子です。
バツ1(20代の出来事)、子どもなし、きょうだいなし、両親は約10年の介護で、数年前に立て続けに亡くなりました。ベンガル猫と2人暮らしです。
50代後半ですが、定年まで働くか否かは考え中です。「体が動くうち」にやりたいことをしたいけど…特にやりたいこともないのが悩みです。
「体が動かなくなったらどうしよう」とも思います。両親共に要介護4でしたから、毎日のようにヘルパーさんが手伝いをしてくれました。
足らない人手は、ご近所に「バイト」を頼みました。親の介護は「金があれば」なんとかなるものです。なければ自分の動力でカバーするしかありません。
とはいえ、もし私が認知症になったら、だれが私の世話をしてくれるのか?
意識はあるけど四肢麻痺の場合、だれになにをお願いすべきなのか?
墓じまいや相続は? それ以前に遺体が発見されるのか?? 心配は尽きません。
死ぬのは怖くありませんが、それまでの道のりが「短く、痛くない」ことを願ってます。
みなしご関連の情報はこちらの「ブログ記事」をご覧ください。