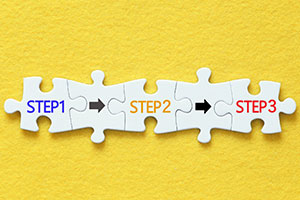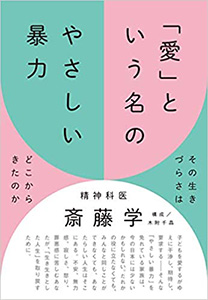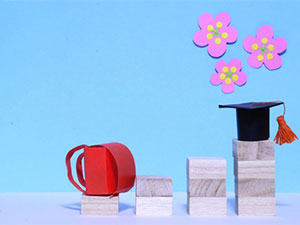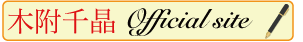「子どものことで相談したいけれど、本人がカウンセリングには行きたがらなくて」というご相談を承ることがしばしばあります。
小学校高学年から中学生、いわゆる思春期の時期になりますと自我が芽生えて主張がはっきりしてきますので、なおさらそのようなお子さんも多いことと思います。
ご本人が来室されなくてもOK

病院の場合、「ご本人が来て診察を受けてもらわないと薬が処方できないので」と言われてしまうこともあるようですが、CAFICではそのようなことはありません。
保護者の方がお子さんを説得しようとしてエネルギーを消耗してしまったり、時期が延ばし延ばしになってしまうよりも、まずは保護者の方に相談にお越しいただくことをお勧めしております。
「本人を見ないとわかりませんよね?」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、保護者の方のお話だけでも十分カウンセラーは対応策を考えることができます。
保護者の方からの情報で、見立て(ご本人がどのような心理状態にあるかの推測と今後の見通し)はだいたいできますし、それに基づいて、ご家族の方がお子様にどう関わっていただくのが良いか、どのように環境を調整していくことが望ましいか、といった点についても考えることができます。
最後までご本人が登場しないことも
カウンセリングではお子さんが相談の場に直接現れなくても、ご家族の心理支援をおこなうことで、ご本人に間接的にアプローチし続けることが可能です。
これは「家族療法」という心理療法の一種を用いた手法で、お子さんの年齢を問わず、適用することができます(お子さんが成人している場合でも大丈夫です)。
ですので、中にはカウンセラーはご本人とは全く会わないまま、保護者の方とのカウンセリングを継続することで、ご本人の問題が改善したり、解決に近づいたりすることもあります。
本格的な‘引きこもり’を防ぐために

特に不登校で家や自室にこもりがちになっているお子さんの場合、「大事な話をしようとすると逃げてしまう」「本人が相談に行くと言ったのに実際にはなかなか動かない」といった状態になることが多く、専門家が関わるタイミングが遅くなりがちです。
不登校やこもりがちの状態が長期にわたりますと、自動的に本格的な引きこもりに移行していく可能性が高くなります。
長期化する前に、そしてできるだけ年齢が若いうちに新たな段階に向かえるよう、まずは親御さんご自身が早めに支援機関とつながることをお勧めしております。