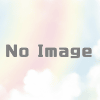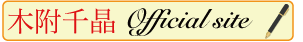CAFIC親子再統合プログラムについて
「しばらく子どもと会えずにいたら、『もう一生(パパもしくはママと)会いたくない』と言われた」
「配偶者が連れ去った子どもと久々に面会することになったが、どのような対応をしたらよいか」
「ずっと一緒に暮らしていなかった子どもと同居することになりそうで戸惑っている」
そんなお悩みに応えるべく、「CAFIC親子再統合プログラム」をつくりました。
「子どもの権利条約」をベースにしたプログラム

同プラグラムの最大の特徴は、子どもの成長発達のための国際的な約束事である「子どもの権利条約」をベースにしていること。もう少しだけ補足すると、「自然な環境としての家庭(実父母)による愛情と幸福と理解のある環境」(条約前文)を子どもが持てるよう援助するプログラムになっていることです。
実父母は子どもにとって「自分を自分たらしめる欠かせない存在」であり、自分の一部です。だからこそ子どもが調和の取れた人格へと成長発達(条約前文)するには、「両親に愛され、望まれて生まれてきた」という確信が必要です。
ところが、そんな単純かつ明快なことが、今の世の中ではなかな実現できずにいます。
間違った「子どもの意見表明」の扱い
とくにやっかいなのが「子どもの意見表明」の間違った扱いです。
2022年に成立したこども基本法に子どもの意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念として掲げられてからというもの、「子どもの意見を大事にしよう!」「子どもの意思を尊重せねば!」と、離婚や同居、子どもがどこで暮らすかなどについても、子どもの意見が最優先だとする考えが広まっています。
例えば、子どもが「別居親に会いたくない」という拒否意思を示せば、「別居親と会わなくてよい」と判断してしまう、というようなことが起きているのです。
しかし、これは子どもの権利条約の「意見表明権」(第12条)を大きく取り違えていると言わざるを得ません。
条約がいう「意見表明権」とは

「子どもが意思決定した内容そのもの」の実現が意見表明権の尊重にあたると考えるのは間違いです。
子どもは、今できる精一杯のやり方で身近なおとなへの呼びかけ(泣く、黙る、暴れる等の欲求も含む愛着行動)ます。こうして表された子どもの思いや願いをおとながきちんと受け止め、応えることで、そこに子どもの成長発達のベースとなる人間関係を子ども自身がつくることを保障すること。それが意見表明権の尊重なのです。
もし、子どもが片方の親を拒否しているとしたら、その子どもの気持ちを受け止めつつ、「どうしたら拒否感が和らぎ、両方の親と良い関係を築けるか」を周囲のおとなが真摯に考え、対策を講じていくことです。
子どもにとって両親はいずれも、唯一無二の存在であり、自分の半身です。そんな大切な親を切り捨て、否定するという残酷な人生を子どもが歩むことのないよう、できる限りのサポートをしていきたいと考えております。 posted by木附千晶