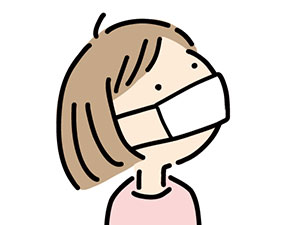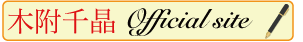長期不登校の対応法
以前に不登校初期・中期の関わり方について書かせていただきました。
・夏休み明け不登校の関わり方
・不登校中期の対応法
今回は、比較的長期の不登校(目安として半年以上)の場合の対応について考えていきたいと思います。
不登校が日常になったときの過ごし方

学校に行っていない状態が数ヶ月以上続くと、ご本人もご家族にとってもそれが‘日常’になってきます。
そのような状況であっても、学校に行くように毎朝声かけをしたほうがいいかどうか、とのご質問をよくいただきます。
親御さんが声をかけて「じゃあ、行こうかな」ということがまずなさそうな印象であれば、登校刺激を続ける必要はありません。
常に学校に行く・行かないばかりを気にしすぎてしまうと、親子ともども疲れてしまったり、親子関係がギクシャクしてしまったりして、あまり良い結果とならないためです。
不登校生も日常を楽しんでいい
「学校にも行っていないのに遊びに行くなんて」という考え方もありますが、お子さんが毎日家にただ籠もっていても、精神衛生上あまり良くはありません。
学校に行っていなくても、ふつうに好きなことをして、罪悪感を持たずに過ごせたほうが、心のエネルギーが充電され、それが状況の改善につながっていきます。
ご家庭によってルールはあっていいと思います(たとえば「平日の日中はゲームをやらない」等)。
ですが、たとえば「毎日学校の授業と同じ時間の勉強をする」といった課題設定は多くのお子さんにとってハードルが高すぎてしまいますので、親子間で話し合って‘ちょっとがんばればできそう'というくらいのルールや課題を決めていけるとちょうどよいかと思います。
不登校から次のステップへ
今回は、不登校中の過ごし方を中心に考えてみました。不登校が長引いてきたときの復帰へのつなげ方については、また回を改めて書きたいと思います。
お子様とのコミュニケーションが難しい・お子様に情緒面の不安定さが見られる、あるいは学校復帰への道筋が見えない、といった場合は、カウンセラーにご相談いただきながら対応を工夫されると良いかと思います。お気軽にお問い合わせくださいませ。
「思春期・不登校に関する相談」はこちらのサイトをご覧ください。